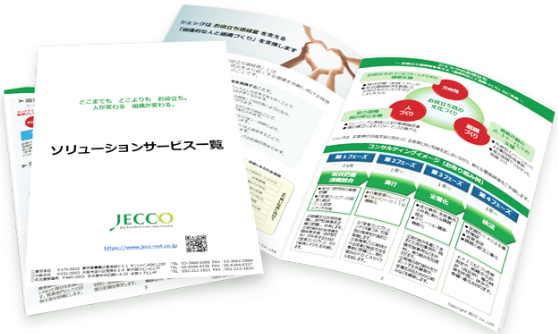「部門間連携」が進まない理由と、その突破口とは?
「情報共有がうまくいかない」
「同じ会社のはずなのに、まるで別の組織のようだ」
「全社視点で動ける人材が育たない」
こうした声は、どの業種・業界でも共通して聞かれます。
私たちはこれまで、多くの企業で「行動変革」を支援してきましたが、部門間連携が進まない背景には、次のような“見えにくい壁”が存在しています。
「連携しづらさ」は、“構造”と“文化”に根がある
部門ごとのKPIや業務フロー、会議体の構成、評価制度など、「縦割り」を助長する構造が、協働を阻む壁を生み出しています。そこに、「うちはうち、よそはよそ」といった心理的な境界線が加わると、実務レベルでの連携はますます困難になります。
つまり、連携を阻んでいるのは「個人の意識の低さ」ではなく、「そうなってしまう仕組みと文化」にあると思われます。
では、どうすれば連携は進むのか?
以下の3つのステップを通じて、部門間の連携を「行動」として実現し、定着を目指します。
-
共通目的の明確化と再定義
まず大切なのは、「自部門の最適」ではなく「全体の成果」に目を向けられる共通目的を、全員が腹落ちする形で定義することです。ここが曖昧だと行動は変わりません。
-
「連携する行動」の具体化と実践
たとえば「他部門と月1回情報交換をする」「プロジェクトには他部門のメンバーを招く」など、連携を「行動」に落とし込み、それをマネジメントの仕組みで後押しします。
-
小さな成功を可視化し、語り合う場づくり
「〇〇部と一緒に取り組んだら、××が改善した」といった成功体験を組織で共有することで、「連携することが当たり前」の文化を醸成していきます。
部門間連携を一時的なプロジェクトやキャンペーンで終わらせず、日々の業務の中に自然と根づかせる─これが目指すべき「連携の文化」です。
連携を文化にするとは、単に「仲良くする」ことではありません。異なる視点や専門性を尊重しながら、目的に向かって力を持ち寄ることが「当たり前」になっている状態を指します。
そのためには、次の3つの土台が不可欠です。
-
部門を越えた「対話と協働」の場があること
異なる部門同士が、普段から気軽に相談し合ったり、共通課題に取り組む場があるかどうか。部門間の接点が「特別なもの」ではなく、「日常の一部」になっているかが問われます。
-
連携を支える「仕組み」があること
たとえば、目標設定や評価指標に「部門間協働」への貢献を含める。プロジェクトチームを常に異なる部門混成にする。こうした制度やルールが、連携を促進する「追い風」になります。
-
マネジメントが「連携の重要性」を日々語り、体現していること
上司自身が他部門と協働し、成功事例や苦労話を部下に共有することで、現場に「連携は推奨されている」というメッセージが伝わります。マネジメントのふるまいが、文化の定着に直結するのです。
「連携の文化」とは、言葉で掲げるだけでは生まれません。小さな行動の積み重ねと、それを促すマネジメント、そしてそれを支える組織設計。この三位一体で、ようやく組織に根付くものです。
今、部門間連携に課題を感じているとすれば、それは単なるコミュニケーション不足ではなく、文化づくりのプロセスがまだ十分に踏めていないだけかもしれません。
組織の力を最大化するには、部門を超えて協働できる「場」と「仕組み」と、それを支える「マネジメントの力」が欠かせません。
私たちは、現場での行動変革を起点に、それを支えるマネジメントを整え、最終的には文化として定着させるまで一貫して支援しています。
「部門間連携」を本気で進めたいとお考えなら、まずは“何が本当の壁なのか”を見つめ直すことから始めてみませんか?
<参考:価値共創型 組織ソリューションの実現>
自社組織の知恵と力を結集し、お客様と共に新たな価値創造ができる「価値共創型 組織ソリューション」をご紹介します。